3月決算の企業では、ちょうど今、顧問税理士からの決算報告が届きはじめる時期ではないでしょうか。
「黒字か赤字か」「税金はいくらか」「納付期限はいつか」。多くの中小企業では、決算の扱いはこの程度で終わってしまうのが実情です。
経営者の多くが、「数字は専門家に任せている」「自分にはよく分からない」と感じているかもしれません。
たしかに、経理や財務には専門知識が必要な場面もありますし、数字を細かく追うことに苦手意識を持つのは自然なことです。
しかし、だからこそ――
経営者には、複雑な会計知識ではなく、「経営の視点」で決算を読み解く“シンプルなフレーム”が必要です。
決算は単なる税務報告ではなく、1年間の経営活動を映し出す“成績表”であり、次の経営に活かすための貴重な情報源でもあります。
専門家任せにするのではなく、「この1年、うまくいったのはなぜか」「来期の改善点はどこか」という問いを自分で立てることが、次の打ち手の質を大きく変えていきます。
本稿では、そうした問いを持つために活用できる、「決算レビュー5STEPフレーム」をご紹介します。
経理や財務の専門知識がなくても実践できる内容なので、ぜひ気負わずに読み進めてみてください。
STEP1:売上・利益の主要因をざっくり棚卸
まず最初に見るべきは、売上と利益の「変動要因」です。
前年と比べて増えたのか、減ったのか。その背景にある要因を、自分の言葉で説明できるでしょうか?
たとえば、「既存顧客の単価が上がった」「大型案件の期ずれがあった」など。ここでは、“専門的な分析”ではなく、“経営の肌感覚”と“数字”の整合性を確かめることが目的です。
STEP2:費用構造の変化を確認
次に確認すべきは、売上総利益(粗利)や販管費の動きです。
粗利率が下がっていないか、人件費や外注費、広告費が前年と比べてどう動いているか。数字の増減だけでなく、その意味を考えることが大切です。
たとえば、「新規採用で人件費が増えた」のであれば、その結果として組織が強くなったのか?売上に寄与したのか?といった“投資対効果”の視点が加わります。
STEP3:キャッシュと借入の動きを確認
利益が出ているのに、手元資金が減っている――そんなときは、キャッシュの流れを確認する必要があります。
営業キャッシュフローがプラスかマイナスか、借入が増減しているか、現預金残高は前年と比べてどうか。資金繰りの感覚を、数字で裏付けることがこのステップの狙いです。
会計ソフトで出せる簡易的なキャッシュフローでも十分です。ここで「資金が詰まりそうなポイント」が見えてきます。
STEP4:BS(貸借対照表)の変化を1枚で見る
貸借対照表(BS)は、会社の“今の姿”を写す鏡です。
- 売掛金や在庫は過剰に増えていないか
- 借入依存度は高まっていないか
- 自己資本比率は落ちていないか
といった基本的な観点だけでも、経営の健全性が見えてきます。「前年と何が変わったか」を1枚の表で比べるだけでも、多くの気づきが得られます。
STEP5:次年度への示唆を言語化
最後のステップは、これまでの4つの確認をもとに、「来期に向けた経営のヒント」を言語化することです。
- どこを伸ばすか
- どこに注意するか
- どの投資を続けるか/見直すか
これは経営者にしかできない問いです。専門的な分析ではなく、「肌感覚」と「数字の事実」をすり合わせ、自社にとっての意味を考える。それが、次年度の打ち手をより確実に、そして納得感をもって進める力になります。
決算書を「経営の道具」に変える
大切なのは、完璧に財務を理解することではなく、“経営に必要な視点”だけをシンプルに持つことです。
「わからないから任せる」ではなく、「わかる範囲で問いを立て、専門家と対話する」。その姿勢が、経営の厚みを変えていきます。
決算書は、過去を整理する資料であると同時に、未来を構想するための“経営ツール”でもあります。
この5STEPをベースに、社内や幹部と対話する場を持つことで、決算は単なる報告書から、組織を前に進める羅針盤に変わっていきます。



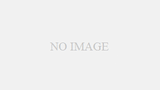
コメント